|
|
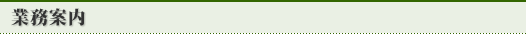
 |
 |
�����ł́A���������ł̎戵�Ɩ��̌�ē���v���܂��B
���s���ȓ_�́A�d�b�A�d�|�l�`�h�k�A���\�����݃t�H�[����育�m�F�肢�܂��B |
 |
 |
�����Ɩ�
�����Ɩ��́A��Y�������c���̍쐬�A�����l�̒����A�s���Y�̖��`�ύX�A���Y�̖��`�ύX�A�����ł̑�Ȃǂ���A�̋Ɩ��Ƃ��čs���Ă���܂��B
�����̑��k�Ɩ��Ƃ��āA�Ɩ��G���A�ł����錧�E��t���E�����s�E��ʌ��E�Ȗ،��ɂ��Ă͏o�����k���\�ł��B
�o�����k�́A�P���ԁ@�S�C�O�O�O�~�{��ʔ�ł��B
���[�����k�͂P�C�O�T�O�~�ł��B�[�������܂ł������v���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�������Y�̂��낢���@�@�@�����葱�̗����@�@�@�@��Y�������c���T���v����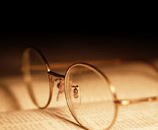 ���⑰�ɂƂ��āA�������Y�͂ƂĂ���ȑ��蕨�ł��B ���⑰�ɂƂ��āA�������Y�͂ƂĂ���ȑ��蕨�ł��B
|
 |
 |
�⌾���쐬
�⌾���쐬�Ɩ��́A�����؏��⌾�̍쐬�����C���Ƃ��Ă��܂��B���M�؏��⌾�A�閧�؏��⌾�ɂ��Ă��쐬�̎w���A�������Y�̒������A���{���Ă��܂��B
�⌾��������ꍇ�A���̂Ƃ��̈⌾���͖@���I�ɗL���ł�����̂Ƃ��܂��B
�⌾��������ꍇ�́A�@�葊�����ɗD�悵�Ĉ⌾���ʂ�ɍ��Y����������܂��B�⌾���͔푊���l�̍ŏI�̈ӎv�\���d���悤�Ƃ������Ƃł��B
�A���A������⌾���ł����Ă��A�S�Ă̍��Y����l�ɗ^���邱�Ƃ͂ł��܂���B�푊���l�̍��Y�̂����A���̑����l�ɑ��Ă͕K�����p�����ׂ����̂Ƃ���銄�������݂��܂��B
������u�◯���v�Ƃ����܂��B
�◯�����҂͔푊���l�̔z��ҁA�q�A���n�����A���n�ڑ��i��P�����j�ƂȂ�܂��B�܂�@�葊���l�̒��ŁA�Z��o���������◯��������܂���B
�◯���́A
�@�z��҂̂݁@�@�P�^�Q
�@�q�̂݁@�@�@�@�@�P�^�Q
�q�Ɣz��ҁ@�@�@���킹�ĂP�^�Q
���n�����̂݁@�@�P�^�R
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ƂȂ�܂��B
�◯����N�Q���ꂽ�ꍇ�A�ƒ�ٔ����ֈ◯���ŎE���������Ď��߂��Ȃ��ƍs���܂���B
���̂܂ܕ��u����ƁA�◯���͎��߂��܂���B
�⌾���Ȃ��ꍇ
�@�⌾�����Ȃ��ꍇ�A�@�葊���l�̒�����A���ʂ̍����l�������l�ƂȂ�܂��B
�@�@��P���ʁ@�@�q�Ɣz���
�@�A��Q���ʁ@�@����i���n�����j�Ɣz���
�@�B��R���ʁ@�@�Z��o���Ɣz���
�@
�@�葊�����̊���
�@��P���ʂ̎q�Ɣz��҂̏ꍇ
�@�@�z��҂��P�^�Q�C�q���P�^�Q�i���l������ꍇ�́A�ϓ�����Ȃ�܂��j
�@�@�A���A�F�m���ꂽ�o�q�̏ꍇ�A���o�q�̂���ɂP�^�Q�ƂȂ�܂��B
�@��Q���ʂ̕���Ɣz��҂̏ꍇ
�@�@�z��҂��Q�^�R�C���ꂪ���킹�ĂP�^�R
�@��R���ʂ̌Z��o���Ɣz���
�@�@�z��҂��R�^�S�C�Z��o�����P�^�S�i���l������ꍇ�́A�ϓ�����Ȃ�܂��j
�@
�@�������������q������ꍇ
�@�����̕����́A�͂��߂��瑊���l�łȂ��������ƂɂȂ�܂��̂ŁA���̑����l�ň�Y�������s���܂��B���������������҂̎q�́A�e����������͂����������������P�����ł��܂���B
�@���q�Ɨ{�q������ꍇ
�@�@���q�A�{�q�Ƃ�����ς�邱�ƂȂ������Ɉ����܂��B
�⌾�����郁���b�g�@�@�@�⌾�̕��@�@�@�⌾���̌��F
|
 |
 |
�ƌn�}�쐬
�����Ɩ���i�߂�ɂ�����A��c�i�c��j�̐��������ȂǁA�F�X�ȏ������W�ł��܂��B�����̏o���A�̐l�̏o���A�͂邩�c��͂ǂ����痈�āA���̎���������̂��낤���H�q�A���A�܂����̐�̎q����������̂�����Ă݂Ă͔@���ł��傤���H
�{�i�I�ȉƌn�}����A�ȈՂ̉ƌn�}�܂ł̍쐬��v���܂��B
���̃y�[�W�� |
 |
�s�n�o�� |